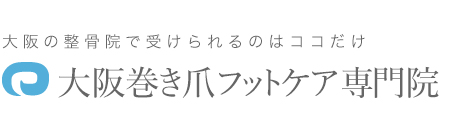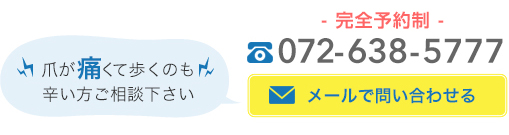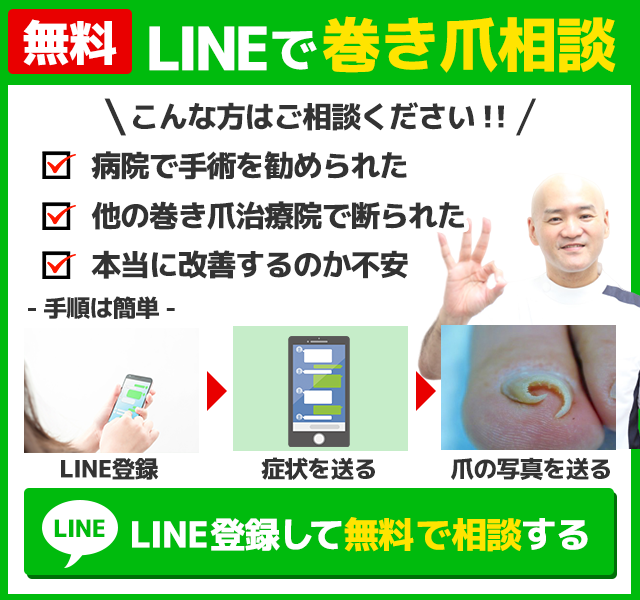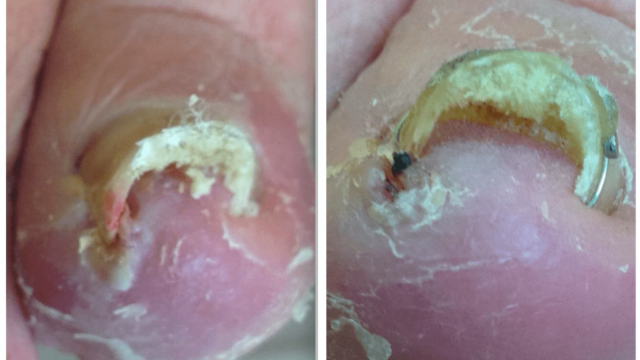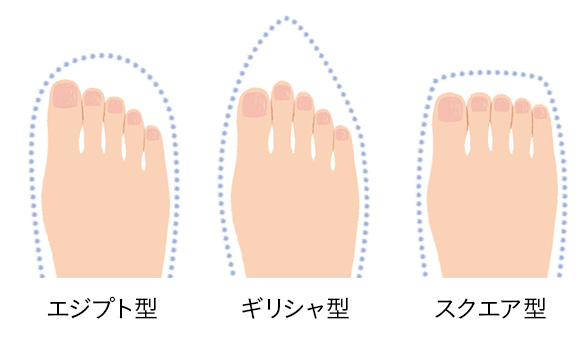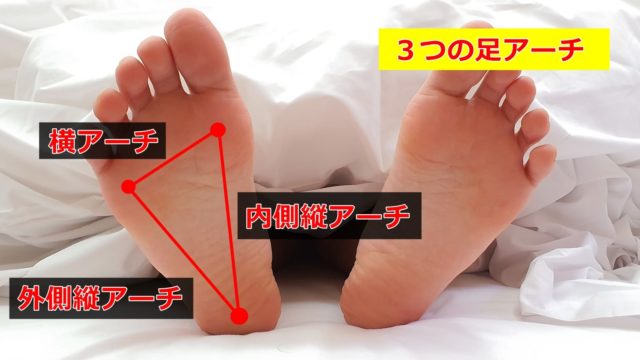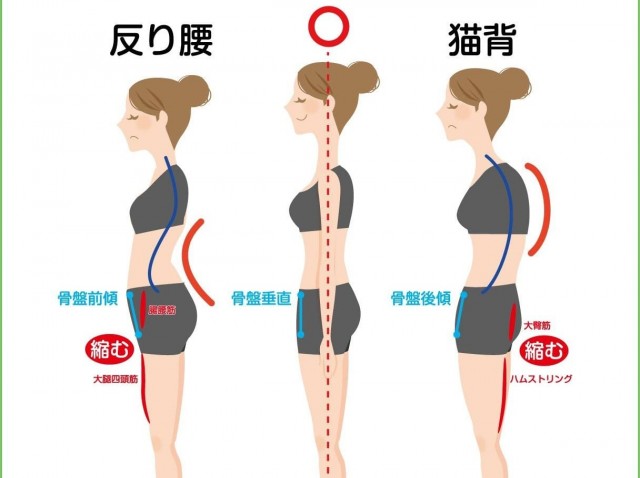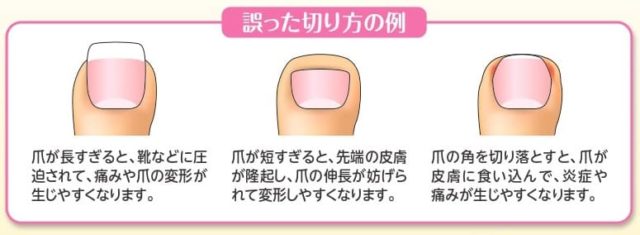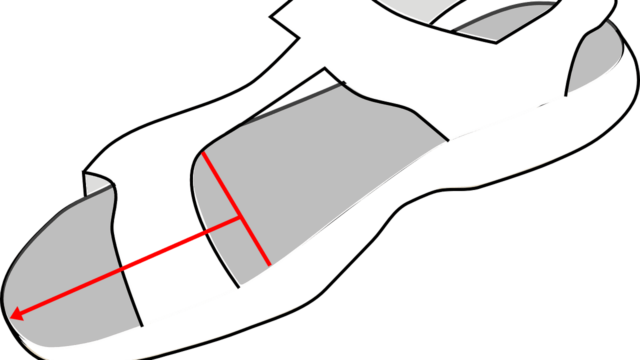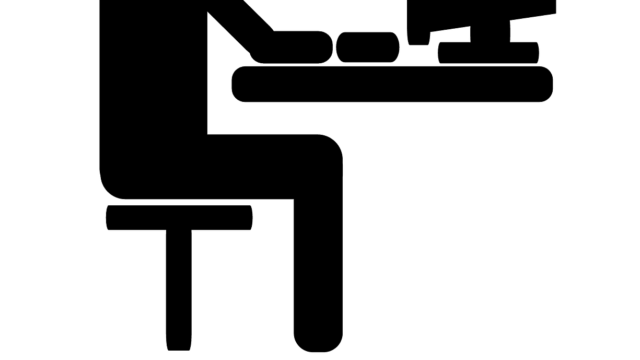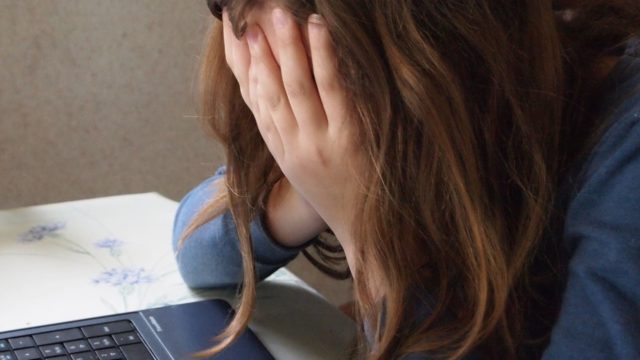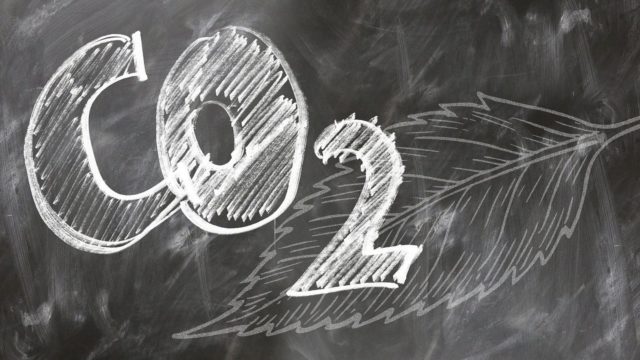冬になると足の爪が割れやすくなる一番の原因は、爪が「乾燥」するからです。爪も水分を含んでいるので、潤いがとても大事なんですよね。
じつは、人の体の中で一番水分が蒸発するのは唇なんですが、意外にもその次が「爪」なんです。
水分不足で唇がカサカサになって割れやすいのと同じで、爪も乾燥することによって割れやすくなってしまいます。ですから、足の爪も指先と同様に、保湿クリームやオイルを塗ったりして、潤いを保っておくことが重要です。
冬の乾燥によって足の爪が割れやすくなる

爪から水分が抜けていって乾燥してしまうと、爪自体が硬くなってしまい、ちょっとした衝撃でも割れやすくなります。
・唇
・かかと
・爪
これらの部位には「皮脂腺」がないので、とくに乾燥しやすいため注意しましょう。
爪が乾燥してくると、表面のツヤがなくなってきたり、縦線が入るようになるので、日頃から自分の足の爪は観察しておくといいですよ。
水分補給で爪のケアをしておこう
爪に十分な水分があると、柔軟性が出てきて割れにくくなります。ちなみに、爪には「12~15%」の水分量が必要だとされています。
もちろん「保湿」することも大切で、手の爪と同様にオイルやクリームを小まめに塗るようにしましょう。冬場の保湿ケアは必須です。
そもそも、足の爪というのは手とは違って、生活をしている中で目でじっくり見たり、丁寧に観察したりする機会がとても少ないです。ですから、お風呂に入る時などのタイミングに合わせて、最低でも「1日1回」はしっかり足の爪の状態を観察をしてください。
ジェルネイルにも気をつけよう
もしも、ジェルネイルをしているなら、より一層「爪の乾燥」には注意してください。ジェルネイルによる悪影響があるからです。
・サンディング(ジェルを乗せる前に爪に傷をつける)
・ジェルオフ(アセトンを使って落とす)
とくに、アセトンは揮発性が高いので、爪の水分まで一気に蒸発させてしまいます。ジェルオフをしたあと、爪が乾燥しやすいのはこの影響です。
他にも、マニキュアやペディキュアを落とすときに使う除光液にも、このアセトンが含まれているので注意しましょう。
爪の保湿方法はこちらの「マニキュアが爪に与える影響とは?巻き爪になるリスクに要注意!」でも解説しているので、よければ参考にしてください。
乾燥した爪を切るときには細心の注意を!
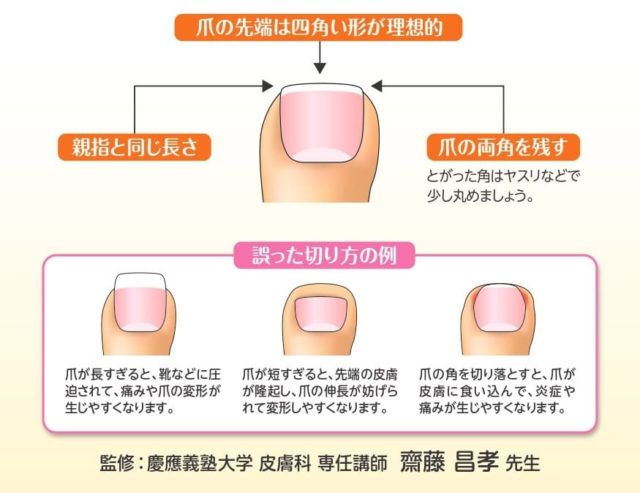
爪が乾燥しているときは、爪の切り方にも注意が必要です。乾燥している爪は、爪切りでも簡単に割れてしまいます。
正しい足の爪の切り方を「足の爪の切り方|巻き爪はこうやって予防しろ!」で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
▼爪切りの注意点
- 乾燥がひどいときは「ヤスリ」を使う
- 爪を一気に切り過ぎない
- お風呂上がりに切る
- 深爪をしない
爪の切り方が悪いと「巻き爪」になりやすくなるので、とくに足の爪を切るときは気をつけましょう。しかも、巻き爪になってしまうと、治るまでにかなり時間がかかります。
いますぐ、足の爪をじっくり見てください。
・爪が変色している
・爪が変形している
・爪が割れている
・皮膚に爪が食い込んでいる etc
足の爪にちょっとでも異変を感じたら注意しましょう。気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。
当治療院では「LINE」にて【無料相談】も受け付けておりますので、ぜひご活用ください!