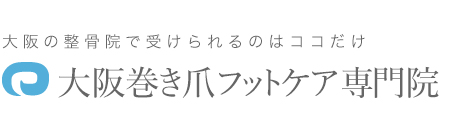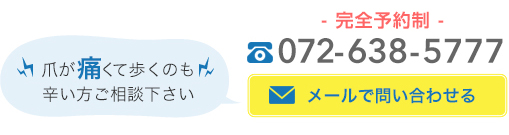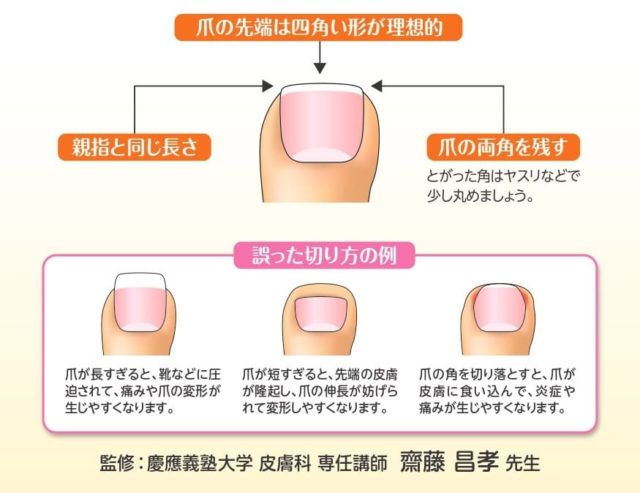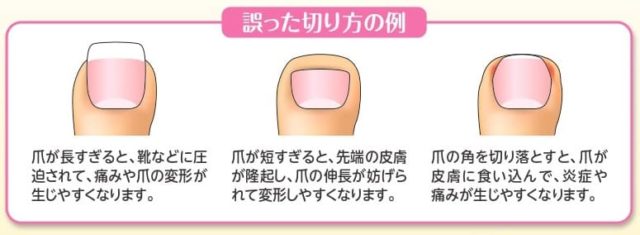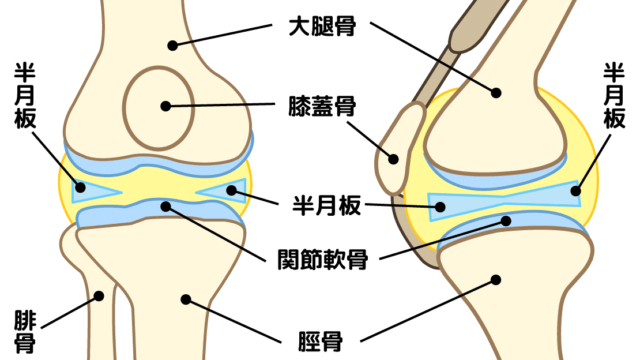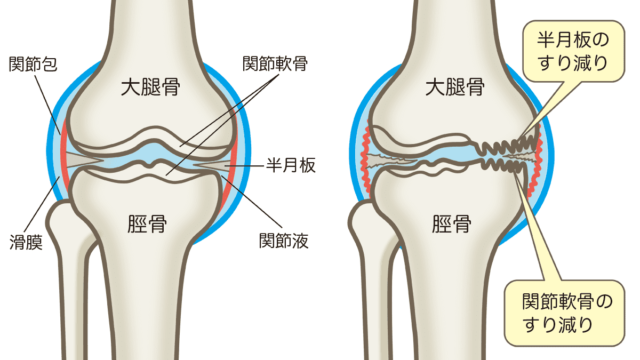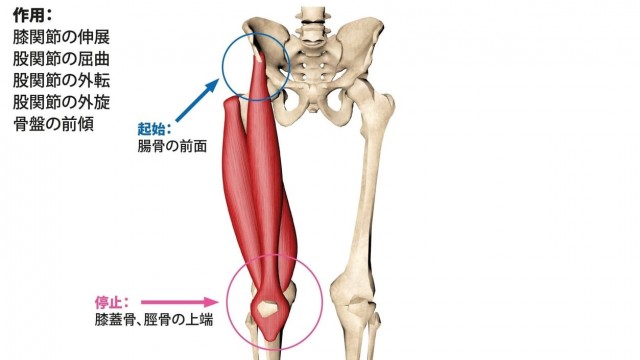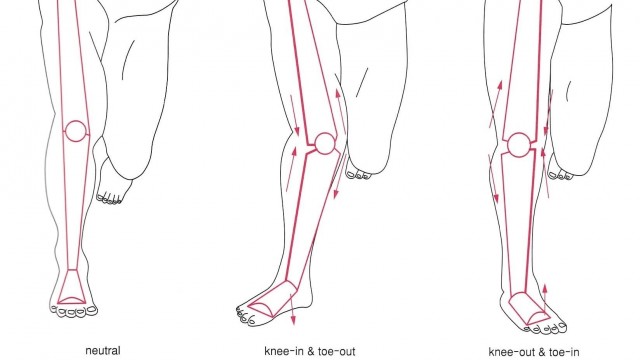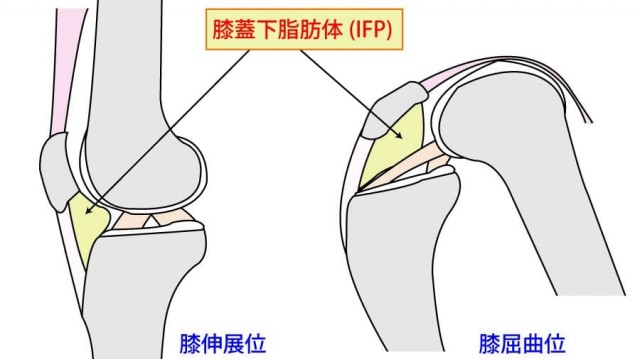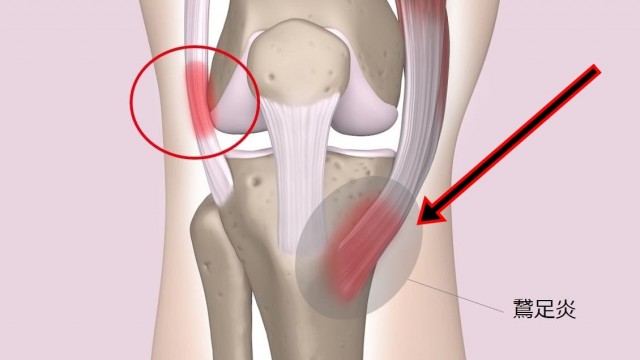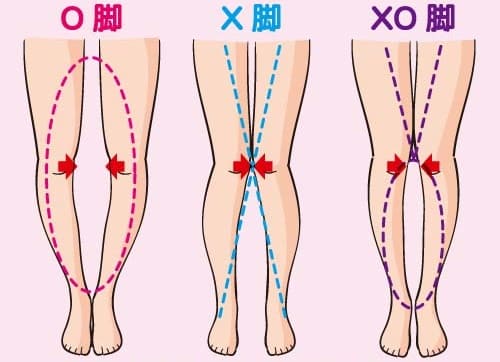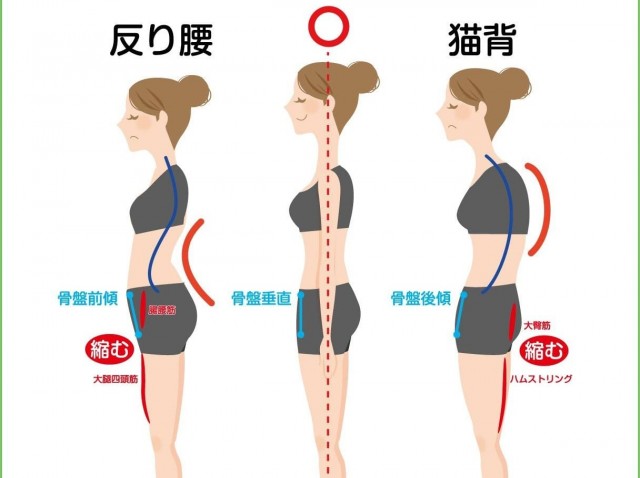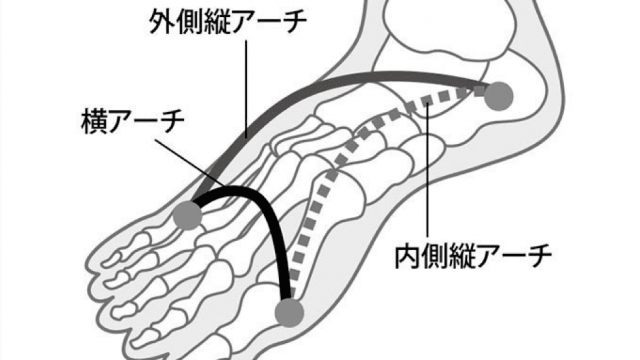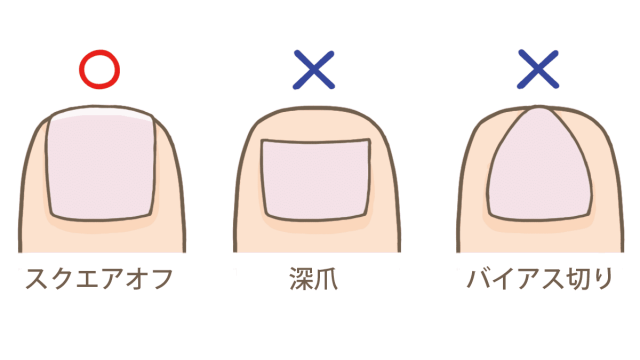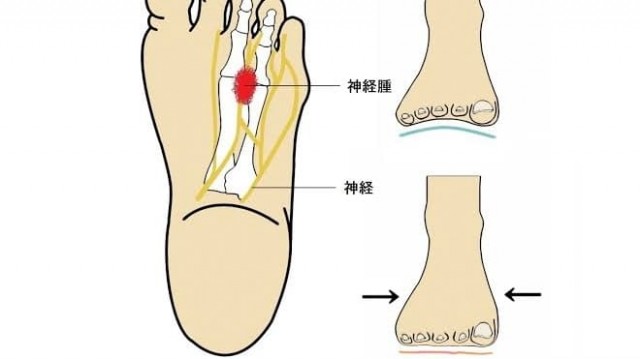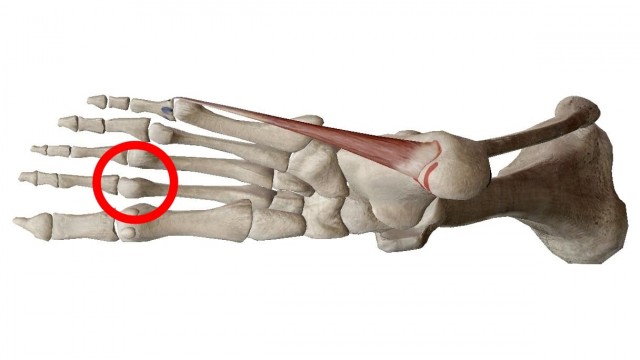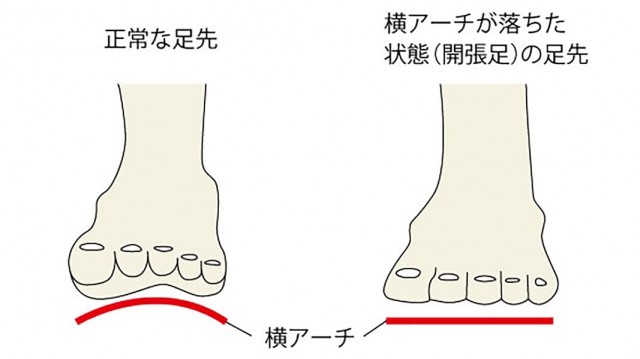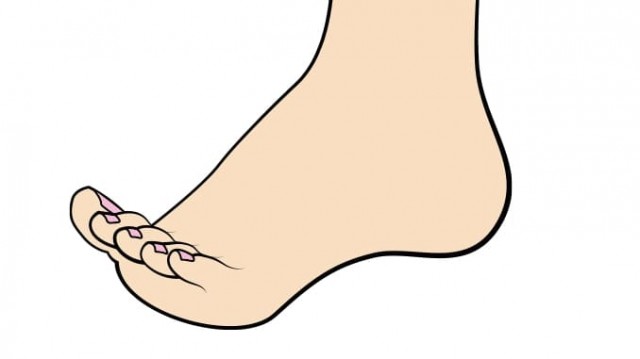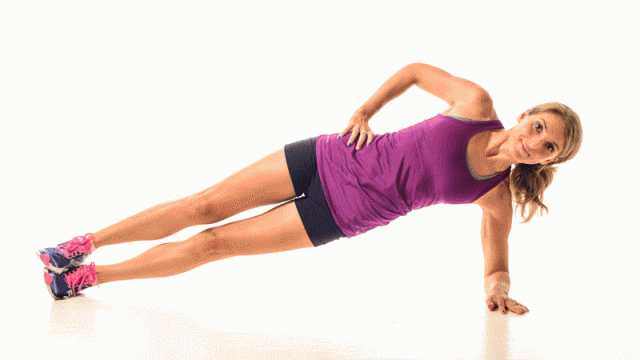春から夏になってくると「サンダルを履く」機会が増えてきますが、サンダルを履くと「爪・つま先」が痛くなるケースが多くなります。
つま先や爪に負担がかかり過ぎると「巻き爪」や「外反母趾」といった、足先のトラブルに発展することもあります。もしも、痛みが出たら注意しましょう。
そこで今回は、サンダルを履いて「つま先」や「爪」が痛くなったとき、その対処・予防法をお伝えします。
サンダルを履くと爪が痛くなる原因
サンダルは、靴にくらべて「露出」している部分が多く、靴ほどピッタリと「フィット」しないので、無意識のうちに「脱げないよう」指先に力が入ります。
さらにヒール部分が高くなっているサンダルを履くと、体重が前がかりになり、つま先に力が入るようになります。
このように
・指に力が入ったり
・つま先に体重がかかる
こういったことで、爪先や親指の爪が痛くなることがあるんですよ。
足の親指に力が入り過ぎると、やがて「巻き爪」や「外反母趾」といったトラブルに繋がるので、注意が必要です。
サンダルで爪が痛くなったときの対処法
つま先や爪が痛くなったときの対処・予防法をいくつか紹介します。
▼つま先や爪が痛くなったら
- サンダルを履かない
- ヒールの低いサンダルを履く
- 鼻緒の付いたサンダルは履かない
- 歩き方に気をつける
- 足の治療をする専門家に相談する
つま先や爪が痛くなってきたら、サンダルを履くのをやめて、専門家に相談してみるのが「最良の対処法」になります。
ヒールの低いサンダルを履く

ヒールの高いサンダルを履いているなら、ヒールが低いものに変えてみるといいです。
つま先とヒールの高さに差があればあるほど、つま先への負担は増えていくので、ヒールの高いサンダルはあまりおすすめできません。
鼻緒の付いたサンダルは履かない

鼻緒の付いたサンダルを履くと、自然と足の指に力が入ります。
そうすると、指先(特に親指)への圧力が高くなるので、痛みの原因になってしまいます。
鼻緒がなく、足の甲にベルトが付いた、こういったサンダル履くといいでしょう。
歩き方に気をつける

サンダルというのは、靴に比べると「つま先が遊んでいる」ので、無意識のうちに力が入りやすいくなります。
・つま先に力が入り出す
↓
・体重が前がかりになる
↓
・つま先に負担がかかる
こうのような悪循環になっていくので、歩くときに「体重をかける位置」を気にするといいです。
具体的には「かかと」と「土踏まず」の中間あたりに、体重をかけて歩くといいでしょう。
歩き方については「内くるぶしを忘れるな!ハイヒールを履いて「長時間」歩くコツがあった」も参考になると思うので、よければ試してみてください!
つま先に異変を感じたら
サンダルを履いていると「つま先が剥き出し」になっているので、あらゆる危険にさらされます。
すでに「巻き爪」や「外反母趾」の症状が出てきていたら、サンダルを履くのは避けましょう。
つま先に異変を感じたら、すぐ専門家に相談するといいですよ!